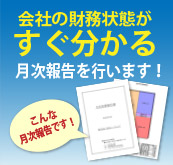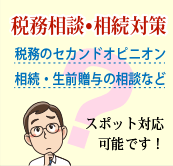生前贈与の重要性
平成27年1月1日以降、相続税の基礎控除額が40%減額されることにより、
(1)相続税が課される人
(2)相続税額をゼロとするために申告する人(※)
の数が多くなることが見込まれています。
(※)相続財産の評価を減額できる相続税法の特例を受けて、
相続税がゼロとなる場合でも申告は必要となります。
なお、相続税の課税対象は、相続により取得した財産から債務を控除した金額となります。
相続税の課税対象 = 取得財産の価額 - 債務

当たり前のことですが、相続税を節税するには取得財産を減らせばよいのです。
しかし、相続開始前3年以内の贈与は税金計算上なかったこととされ、相続税の計算に組み込まれてしまいます。
よって、生前贈与を有効に利用するためには、実行とともに「早期」に「継続して」行うことが重要なのです。
そもそも贈与税とは
生前贈与が重要と書きましたが、贈与した場合には一般的に贈与税が課税されます。
(1)贈与税の納税義務者
原則として個人からの贈与によって財産を取得した個人です。
(2)基礎控除額
暦年課税の場合、「110万円」です。
よく勘違いされる方がいますが、贈与する(あげる)人の贈与金額が110万円ではなく、
贈与される(もらう)人の贈与を受けた金額が110万円を超えると贈与税が課税されるので、
注意が必要です。
(例)贈与税が課税されないように、父、母が100万円ずつ子供に贈与した。
→100万円×2-110万円(基礎控除額)=90万円が贈与税の対象となり、
子供は贈与税の申告、納税をする必要があります。
(3)贈与税率
贈与税の税率、相続税の税率は以下のとおりです。
贈与税の税率は、非常に高く設定されています。
相続税の節税を考えるあまり、高い贈与税を支払わないように注意して、
生前贈与を行わなければなければなりません。
| 基礎控除等の後の課税価格 | 税率 | 控除額 | |
| 超 | 200万円以下 | 10% | ー |
| 200万円超 | 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超 | 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超 | 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超 | 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 | |
| 法定相続分の各相続人の取得価格 | 税率 | 控除額 | |
| 超 | 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 1,000万円超 | 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 | 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 | 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 | |
生前贈与の方法
一般的な方法としては、下記の方法が挙げられます。
他の贈与方法については、当事務所にお問い合わせください。
基礎控除額は、財産に比して少額と考えられますから、長期間にわたり計画的に贈与することが必要です。

(1)土地の贈与
贈与税の計算上、土地の贈与価額は原則として路線価
により評価されます。
路線価は、一般的に公示価格の8割程度と言われていますから、現金で贈与するより2割程度課税対象額を低くすることができます。
しかし、贈与するごとに不動産登記料、不動産取得税及び登録免許税が発生します。
結果的に贈与税より高い手続き料を払う可能性があるので、試算を行ったうえで実行されるのが
よいと考えます。
(2)収益建物(賃貸物件)の贈与
収益建物の贈与を行った場合、贈与後の収益は建物をもらった人のものになります。
贈与を行わなければ、今までどおり贈与した人の収益(財産)となり、将来的に相続税の課税対象となる
可能性が高いですから、その分相続税を軽減できることになります。
(3)その他贈与税の特例を活用した贈与
贈与を行う際の注意点
「贈与の成立」について、税務上問題になることがあります。
要は、① 贈与は成立していない → ② 贈与がなかったので贈与をした人(相続税の場合亡くなった人)からの財産の移転がなかった → ③ 相続税の課税対象とするよ、と税務署より指摘される可能性があるということです。
贈与は、贈与する人が贈与します、贈与される人が受け取りましたと双方の合意がある場合に成立します。
しかし、税務署に贈与の有無を指摘された場合に、これを立証することは口頭のみでのやりとりですと、非常に困難です。
そのため、贈与があった(成立している)ということを主張できるように、下記のような手続きを行っておくことが重要です。
(1)贈与契約書を作成する
双方の合意を書面で明確にします。
公証人役場で確定日付を取っておくと、日付を遡って
作成したのではないとの立証ができるので、よりよいと考えられます。
(2)贈与が行われた履歴を残す
客観的資料で贈与の事実を立証できるようにすることも大切です。
金銭の贈与であれば銀行振込を行い、通帳に贈与者、贈与金額が残るようにするここと、土地建物の贈与であれば、所有権の移転登記を移転事由:贈与できちんとおこなうことが履歴を残すことになります。
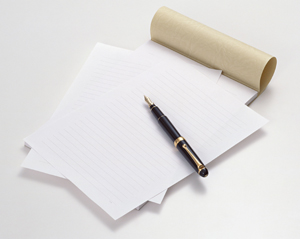
(3)贈与税の申告を行う
贈与金額が基礎控除額(110万円)を超える場合には、贈与税の申告が必要です。
当たり前のことですが、これも立証証拠の一つとなりますので、忘れずに申告することが必要です。
(ただし、贈与税の申告書を提出しただけでは、贈与を行ったとの明確な立証資料とはなりません。
あくまでも契約書の作成の有無、お金の流れ、モノの流れなどいろいろな状況を加味して判断されるので留意が必要です。)
上記は、お読みやすくするため、原則的なことを中心に記載しています。
相続税、贈与税は事例により、適用できる規定、適用できない規定や注意すべき点が異なってきます。
その点、ご了承ください。
具体的なご相談は、お気軽に当事務所にご連絡ください。 >>> お問い合わせ